「日本巫女史/第一篇/第四章/第二節」の版間の差分
細 踊り字の展開。 |
|||
| 39行目: | 39行目: | ||
'''三 剣''' | '''三 剣''' | ||
諾尊が黄泉醜女に追われた折に『<ruby><rb>御佩</rb><rp>(</rp><rt>ミハカ</rt><rp>)</rp></ruby>せる<ruby><rb>十拳剣</rb><rp>(</rp><rt>トツカノツルギ</rt><rp>)</rp></ruby>を抜きて、後手に<ruby><rb>揮</rb><rp>(</rp><rt>フ</rt><rp>)</rp></ruby> | 諾尊が黄泉醜女に追われた折に『<ruby><rb>御佩</rb><rp>(</rp><rt>ミハカ</rt><rp>)</rp></ruby>せる<ruby><rb>十拳剣</rb><rp>(</rp><rt>トツカノツルギ</rt><rp>)</rp></ruby>を抜きて、後手に<ruby><rb>揮</rb><rp>(</rp><rt>フ</rt><rp>)</rp></ruby>きつつ逃げ来ませる』とあるのは、剣に呪力のあったことを物語る最古の記事である。「神武記」に帝が紀州熊野村に到りしとき荒振神に逢い、 | ||
: 神倭伊波礼毘古命(神武帝)倏忽に<u>をえ</u>(中山曰、毒気に中ること)まし、及御軍皆<u>をえ</u>て伏しき。此の時に、熊野の高倉下、<ruby><rb>一横刀</rb><rp>(</rp><rt>タチ</rt><rp>)</rp></ruby>を齎ちて、天神の御子の伏せる地に到りて献る時に、天神の御子、即ち<ruby><rb>寝起</rb><rp>(</rp><rt>サメ</rt><rp>)</rp></ruby>まして、長寝しつるかも、と<ruby><rb>詔</rb><rp>(</rp><rt>ノ</rt><rp>)</rp></ruby>りたまひき。故その横刀を受取たまふ時に、その熊野山に荒ぶる神、<ruby><rb>自</rb><rp>(</rp><rt>オノヅカ</rt><rp>)</rp></ruby>ら皆切仆さえて、其の<u>をえ</u>伏せる御軍、悉に寝起たりき云々。 | : 神倭伊波礼毘古命(神武帝)倏忽に<u>をえ</u>(中山曰、毒気に中ること)まし、及御軍皆<u>をえ</u>て伏しき。此の時に、熊野の高倉下、<ruby><rb>一横刀</rb><rp>(</rp><rt>タチ</rt><rp>)</rp></ruby>を齎ちて、天神の御子の伏せる地に到りて献る時に、天神の御子、即ち<ruby><rb>寝起</rb><rp>(</rp><rt>サメ</rt><rp>)</rp></ruby>まして、長寝しつるかも、と<ruby><rb>詔</rb><rp>(</rp><rt>ノ</rt><rp>)</rp></ruby>りたまひき。故その横刀を受取たまふ時に、その熊野山に荒ぶる神、<ruby><rb>自</rb><rp>(</rp><rt>オノヅカ</rt><rp>)</rp></ruby>ら皆切仆さえて、其の<u>をえ</u>伏せる御軍、悉に寝起たりき云々。 | ||
2008年9月20日 (土) 16:47時点における版
第二節 呪術のために発達した器具
呪術のために発生したものと、これに反して、発生の理由は他にあるも、呪術に用いられたために一段の発達をしたものとあるが、茲には是等を押しくるめて記すとする。ただ恐れるのは、本節における私の考覈が、従来の研究と異るところがあるので、異説を立てるに急なる者のように誤解されはせぬかと云う点である。併し私としては決してさる野心の毫も有せぬことを言明する次第である。
一 玉
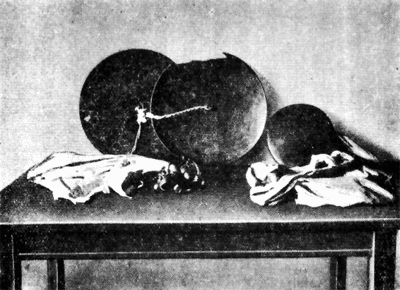
我国に古く重玉の思想の在った事は言うまでもない。否々、思想と云うよりは、信仰と云う方が適当に想われるまでに、玉を重んじていた。而してその玉は概して
- 昔丹波国桑田村有人、名曰
甕襲 、則甕襲家有犬、名曰足往 、是犬咋山獣名牟士那 、而殺之、則獣腹有八尺瓊勾玉、因以献之、是玉今在石上神宮。
とあるのは、山獣の腹に勾玉の在ったということが、当時の民族心理からは、一つの神恠として見られたのであるが、併しその勾玉が石上神宮に納められたのは、玉を重く信仰した結果に外ならぬのである。
全体、我国の勾玉に就いては、考古学的にも民俗学的にも研究されるべき余地が少からず残されているのである。就中、私の興味を唆るものは、勾玉の形状は何を
併しながら、私に言わせると、此の考察は余り常識的であって、我国の古い民俗に適応せぬものがあるように想われる。私は茲に勾玉を研究するのが目的でないから、結論だけを簡単に記すとするが、私の信ずるところでは、勾玉は腎臓の
由来、我国では心の枕辞に村肝の二字を冠していて、此の村肝とは『肝は七葉
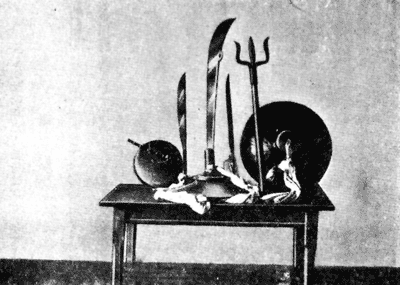
然るに、此の腎臓の色は紫であって、それが
猶お此の機会において併せ考うべき事は、古代人は勾玉を霊魂の宿るもの〔五〕、若しくは霊魂の形と思っていたと云う点である。これも理由を述べると長くなるので結論だけ言うが、我国で、魂と玉を、同じ
二 鏡
鏡の起りは「鑑」であって、其の用途は、陽燧にあったと云われているが、我国に渡来するようになってからは、専ら呪術の具として用いられていた。「景行紀」十二年秋九月の条に、神夏礒媛(巫女にして魁帥を兼ねたもの)が参向する際に、
- 則抜磯津山賢木、以上枝挂八握剣、中枝挂八咫鏡、下枝挂八尺瓊、亦
素 幡樹于船舳。
とあるのは、当時、呪具として最高位の鏡、剣、玉を用いたものであって、これと全く同一なる記事が「仲哀紀」にも載せてある所を見ると〔六〕、かなり広く行われていたことが知られるのである。而して鏡が照魔の具として用いられたこと、及び巫女に限って鏡を所持した事などは、共に鏡が呪具として重きをなしていたことが想像される。「万葉集」巻十四の『山鳥のをろの
三 剣
諾尊が黄泉醜女に追われた折に『
- 神倭伊波礼毘古命(神武帝)倏忽にをえ(中山曰、毒気に中ること)まし、及御軍皆をえて伏しき。此の時に、熊野の高倉下、
一横刀 を齎ちて、天神の御子の伏せる地に到りて献る時に、天神の御子、即ち寝起 まして、長寝しつるかも、と詔 りたまひき。故その横刀を受取たまふ時に、その熊野山に荒ぶる神、自 ら皆切仆さえて、其のをえ伏せる御軍、悉に寝起たりき云々。
と記せるも、亦た剣に呪力のあった事を証明しているものである。而して斯くの如き記事は、我国の一名を『
四 比礼
大己貴命が素尊の許に往き、蛇室に寝るとき須勢理媛より蛇ノ比礼を与えられ、且つ『その蛇
本居宣長翁は『比礼とは(中略)、何にもまれ打振る物を云ふ、されば魚の
私は茲に服飾史の上から比礼の研究を試みることは措くが、是等の諸説のうち、飯田翁の考証に左袒するものである。而して此の服具を、或は蛇比礼と云い、或は蜂比礼と云うたのは、呪具としての用途によって名づけたものと考えている。巫女の比礼に対して、覡男の
五 櫛
素尊が八岐大蛇を退治して、奇稲田媛を救うことを「古事記」には『速須佐之男命、乃ち其の童女を湯津爪櫛に取成して,
然るに、
猶お此の種に属する呪具のうちに、幡、幟、幣などを数える事が出来るのであるが、是等は後に記述する機会もあろうと思うので、今は触れぬこととした。
- 〔註一〕
- 故坪井正五郎氏を始め、多くの人類学者や、考古学者は、皆この獣牙説を採っていて、幾多の著書や雑誌に、此の事が載せてある。従って天下周知の事と思うので、書名や、誌名は、煩を避けて省略した。猶お勾玉に就いては、谷川士清翁の「勾玉考」が、よく史料を集めて、古代の重玉信仰を説いている。参照せられたい。
- 〔註二〕
- 「冠辞考」巻下。その条。
- 〔註三〕
- 柳田国男先生の著「後の狩詞記」及び「民族」第三巻第一号所載の早川孝太郎氏の「参遠山村手記」及び同氏著「猪・鹿・狸」(第二叢書本)を参照せられたい。
因みに言うが、柳田先生の「後の狩詞記」は稀覯の書であるので、茲にその一節を摘録すると「コウザキ。猪の心臓を云う。解剖し了りたるときは、紙に猪の血液を塗りて之を旗とし、コウザキの尖端を切り共に山神に献ず」とある。 - 〔註四〕
- 先年雑誌「太陽」へ拙稿「枕辞の新研究」と題して掲載したことがある。誌上には匿名になっている。号数は失念したが、大正六七年ごろの発行である。
- 〔註五〕
- 瓢が魂の入れ物であるという古代人の信仰に就いては、柳田国男先生が「土俗と伝説」の第二号から連載された「杓子と俗信」の中に述べられているし、更に近刊の「民俗芸術」第二巻第四号所載の「人形とオシラ神」のうちにも記してある。而して、我国の古代において、墳墓を瓢型に築いたのも、亦此の信仰に由来しているのである。人魂の形は、杓子に似ているとは、今も言うところであるが、古代人は、勾玉の形を人魂の形に連想していたことも、考慮のうちに加うべきである。
- 〔註六〕
- 「仲哀紀」八年春正月の条に『筑紫伊覩県主祖五十迹手、聞天皇之行、抜取五百枝賢木、立于船之舳艫、上枝掛八尺瓊、中枝掛白銅鏡、下枝掛十握剣、参迎于穴門引嶋而献之』と載せてある。
- 〔註七〕
- 山鳥の尾の呪力に就いては、曾て「土俗と伝説」第三号に「一つ物」と題して拙稿を載せたことがある。
- 〔註八〕
- 「古事記」神代巻。
- 〔註九〕
- 「古事記伝」巻十(本居宣長全集本)。
- 〔註一〇〕
- 「増補語林倭訓栞」その条。
- 〔註一一〕
- 「延喜式祝詞講義」巻九の細註。下野国足利郡は、私の故郷である。従って、此の地方の民俗には、失礼ながら鈴木翁よりは通じていると云っても差支ないと信ずるが、私の知っている限りでは、此の地方で、婦女が手拭を冠って他人の前へ出るのは、髪の乱れを隠すためであって、領巾の遺風などとは考えられぬ。これは鈴木翁の思い過ごしであらねばならぬ。それに、領巾は、冠る物ではなくして、垂れるものである。
- 〔註一二〕
- 「日本書紀通釈」巻二十六。
- 〔註一三〕
- 女子の有夫の標識には、種々なる民俗がある。眉を払うのも、歯を染めるのも、更に櫛を挿すのも皆それである。詳細は拙著「日本婚姻史」に諸国の例を集めて載せて置いた。宮城県の磐瀬郡では、昔は未婚者と既婚者の区別は、櫛を挿すと挿さぬとにあったが、近年では、誰も彼も櫛を挿すので区別に苦しむと、同郡誌に記してある。